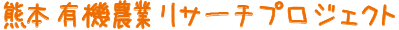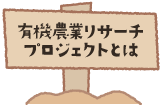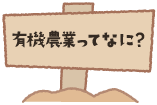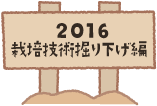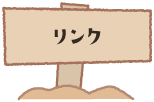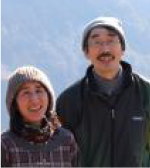中山間地に新規就農者して15年
名古屋で会社員として勤めていた頃から、田舎で暮らしたいという希望があり、自分たちを含め、食べる人の安全を第一に考えたいという思いで有機農業を選び、1999年に就農したそうだ。
まだ新規就農が珍しい時代に、上手く軌道に乗った要因としては、①早い時期に主体となる作目が固定できたこと、②早い時期にある程度の販路が固定できたことではないだろうか。
全て借地で、その分耕作できる農地の条件は限られるわけだが、そうした中でも施設(ビニールハウス等)を使わずに安定した経営ができているところは素晴らしい。
生活や暮らしぶりを見ていると、中山間地ならではの良さに気づかされ、都会での生活よりもこちらでの生活に向いている人もたくさんいるのではないかと感じた。大金持ちになることはできないかもしれないが、その良さに惹かれた人たちが少しでも中山間地で就農してほしいと思わせる事例である。
<栽培品目>
「有機でできないものは作らない」が基本。
メインはお米とミョウガ。それらの時間が空く時期には何ができるかということで作付けを決めている。お米、ミョウガ以外は保管がきく根菜類の作付が主体となっているが、お茶(7a)、タマネギもやっている。
ミョウガの栽培は山都町にある出荷グループ「御岳会」メンバーに栽培、出荷を勧められたのがきっかけだが、夏場の草取り、収穫、出荷準備が大変。対策としては、冬から春にかけて、落ち葉と刈り草をミョウガの畑に敷きつめる。ミョウガは病害虫による被害が少なく長雨にも強いし、元手がかからず、資材も必要としないのが長所。
<ほ場環境>
田んぼは近くにまとまっているが、畑は4か所に分散している。全て借地。標高は約400mの中山間地。堆肥のすきこみと、土壌改良材の施用を行っている。
【土質について】
自宅近くの農地は粘土質(ベタベタしている)なので、田んぼにしている。家から最も離れている、車で15分のところには黒ボク土の農地もあり、そこにはニンジンを植え付けている。
<施肥>
堆肥は鶏ふんとおがくずが混ぜてある醗酵堆肥を購入。
・土壌改良にはサンライム(カキ殻石灰)を使用している。
・土壌分析は数年に一度やっている。
・冬の間に、ミョウガの畑には落ち葉と刈り草を入れている。
①ぼかし有機肥料 バランス684 N:P:K=6:8:4(%)
②有機763 N:P:K=7:6:3(%)
③サンライム(カキ殻石灰)
④天然硫マグ24
※全て購入で、自家製肥料はなし。
①~③は元肥に使用。④は元肥、追肥に使用(イネへの追肥は7月)。追肥が必要な果菜類の栽培面積は少ないので元肥が主体となる。施肥量の基準は窒素分をベースに考えていて、基本的にチッソ6%のものを使っている。 水稲は、窒素5kg/10aをめどに、肥料を80kg、畑は、同10kgをめどに、肥料を200kgいれる。
【育苗土について】
稲の育苗は普通の苗箱を使いますが、箱には山土しか入れません。苗代の床になるところに、有機肥料(チッソ6%)をいれます。苗箱1枚当たり肥料100gを目安に施用。
野菜は有機の育苗土を購入。鶏ふん、山土、ピートモスが主成分で、本来はレタスなどの葉もの用の床土らしい。
<雑草対策>
【田の除草】
アイガモとジャンボタニシで除草。完ぺきではないので、少しは手で草取りしたり、手で株まわりをかき回したりする。
アイガモは虫を取ってくれる。昨年はウンカの発生が際立った年だったが、アイガモの入っていた田んぼでは被害がなかった。周囲にネットを張るなど手間はかかるが、除草効果は高い。
※井出の水が止まるので、冬期たん水はできない。
【畑の除草】
サトイモ、カボチャ、タマネギにはポリマルチを使用し、株まわりを手で除草するようにしている。畝間の通路は管理機、ホー、鍬を使って除草する。古ビニールを使うこともある。ニンジンの除草は基本的に手取り。太陽熱処理をすることで少しは手間が省ける。ミョウガの畑には冬期に落ち葉や刈り草を敷くが、それでも除草は必要になる。5、6月に2まわりくらいする。
<病害虫対策>
【イネの病虫害】
いもち病対策としては、肥料をやりすぎないこと。冷や水もよくないので、昼間の暑い時間帯に冷たい水を入れないのが基本。
ウンカの被害に昨年初めてあった。アイガモを入れていない田んぼがやられた。
【畑の病害虫】
輪作というよりは、してはいけない連作を避けるようにしている。サトイモは連作しないで3~4年はあける。ナス科も連作はしないで5年はあける。
品種の選択としては、病気になりやすいものは避ける。そもそも病害虫の被害を受けにくい作物を栽培するようにしている。
防虫ネットについては、夏レタスには4mm目と大きめの目合いのネットを使う。蛾、チョウの侵入を防ぐためのもので、目が小さすぎるとこの時期は中が蒸れてしまう。
肥培管理による病害虫対策としては、肥料をやりすぎないよう気をつけている。追肥はマグネシウム、カルシウム主体。
【鳥獣害】
カラス…黒テグスで被害を防ぐ。透明のテグスよりも効果が高い。ロケット花火も使用。
イノシシ…電柵を使用。ミョウガの畑には張らない。ミョウガの畑に入ることもあるが、ミョウガそのものへの被害はない。爆竹も使用。作業後の帰り際に、爆竹を鳴らして帰る。
シカ…田植え後の苗を食べに来る。電柵の線を3段にすると電気代が高くなるので、いちばん上の段は線だけ張って電気は通していない。